因数分解の公式が多すぎて覚えられない、どの問題でどの公式を使えばいいか分からない…。そんな悩みを抱えていませんか?この記事は、因数分解でつまずいている学生のあなたのための【完全ガイド】です。
中学・高校で習う公式を一覧で総復習し、複雑な式でもスラスラ解けるようになる「5つの実践テクニック」を例題付きで丁寧に解説します。「たすきがけ」のコツや、「なぜ因数分解を学ぶのか」という疑問にも答えます。この記事を読み終える頃には、因数分解への苦手意識が自信に変わっているはずです。
そもそも因数分解とは?なんのために(いつ)使うの?
数学の授業で「まず、これを因数分解して…」と当たり前のように言われても、「そもそも、なぜそんな面倒なことを?」と疑問に思うのは、とても大切なことです。その「なぜ」が分かれば、学習の目的がはっきりします。
因数分解は「かけ算の形」に戻す作業
「展開」は、カッコを外して足し算や引き算の形(和の形)にすることでした。
例えば、(x+2)(x+3) を展開すると x^2 + 5x + 6 になります。
因数分解は、そのまったく逆の操作です。
足し算や引き算でつながっている式を、カッコ(など)でくくった「かけ算の形」(積の形)に戻すことを指します。
x^2 + 5x + 6 → (x+2)(x+3)
このとき、かけ算の形を作っている一つひとつのパーツ(この例では x+2 と x+3)を 因数 と呼びます。
具体的にいつ使う?:2次方程式・不等式を解くため
では、なぜわざわざ「かけ算の形」に戻すのでしょうか?
その最大の理由は、「方程式が圧倒的に解きやすくなるから」です。
例えば、 x^2 + 5x + 6 = 0 という2次方程式を解くことを考えてみてください。
足し算の形のままでは、x にどんな数字を入れたら0になるか、見つけるのは大変です。
しかし、これを因数分解して (x+2)(x+3) = 0 と「かけ算の形」にするとどうでしょう?
かけ算して答えが 0 になるのは、どちらか(あるいは両方)が 0 の場合だけです。
つまり、「x+2=0」または「x+3=0」となれば良いことが分かります。
よって、x = -2、x = -3 と、一瞬で答えが見つかります。
このように、因数分解は、これから学ぶ2次方程式、2次関数(グラフのx軸との交点を見つける)、さらには高次方程式や不等式を解くための、非常に強力な道具(テクニック)なのです。
【中学レベル】まずは必須!基本の因数分解公式4選
ここからは、具体的な公式と使い方を見ていきましょう。まずは中学の数学で習う、最も基本的で重要な4つの公式です。高校数学の問題も、土台となっているのはこれらの公式です。忘れているものがないか、例題と一緒に確認してみてください。
| ① 共通因数でくくる | ma + mb = m(a+b) |
| ② 平方の公式 | a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 |
| ③ 平方の公式(マイナス版) | a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 |
| ④ 和と差の積の公式 | a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) |
① 共通因数でくくる
これが因数分解のすべての基本です。「まず共通因数でくくる」は、どんな問題でも最初に考えるクセをつけましょう。
共通因数とは、式の中のすべての項が持っている、共通のかけ算の要素です。
【例題】
2x^2 + 6xy を因数分解しなさい。
【解き方】
- 数字を見る:「2」と「6」の最大公約数は「2」です。
- 文字を見る:「x^2(xが2個)」と「xy(xが1個とyが1個)」に共通しているのは「x(が1個)」です。
- 共通因数を特定:したがって、共通因数は「2x」です。
- くくり出す:2x で全体をくくり出し(割り算するイメージ)、残ったものをカッコに入れます。
2x^2 + 6xy = 2x \times x + 2x \times 3y = 2x(x + 3y)
【答え】 2x(x + 3y)
② 平方の公式
「平方の公式」と呼ばれるものです。式の「両端」が何かの2乗になっていて、真ん中の項が「両端の2乗する前のものをかけて2倍」になっていたら、この公式が使えます。
【例題】
x^2 + 10x + 25 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 両端を見る:x^2 は「x」の2乗、+25 は「+5」の2乗です。
- 真ん中を確認:x と +5 をかけて2倍すると、2 \times x \times 5 = 10x となり、真ん中の項と一致します。
- 公式を適用:(x+5)^2 の形にまとめます。
【答え】 (x+5)^2
③ 平方の公式(マイナス版)
②の公式の、真ん中の符号がマイナスになったバージョンです。考え方はまったく同じです。
【例題】
x^2 - 12x + 36 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 両端を見る:x^2 は「x」の2乗、+36 は「+6」または「-6」の2乗です。
- 真ん中を確認:真ん中の項が「-12x」とマイナスなので、「-6」の方を使ってみます。
x と -6 をかけて2倍すると、2 \times x \times (-6) = -12x となり、一致します。 - 公式を適用:(x-6)^2 の形にまとめます。
【答え】 (x-6)^2
④ 和と差の積の公式
これは最も見つけやすい公式かもしれません。「(何かの2乗)-(別の何かの2乗)」という形になっていたら、この公式を使います。項が2つしかないのが特徴です。
【例題】
x^2 - 49 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 形を確認:x^2 は「x」の2乗、 49 は「7」の2乗です。
- 公式を適用:「a^2 - b^2」の形(a=x, b=7)になっているので、「(a+b)(a-b)」に当てはめます。
(x+7)(x-7) となります。
【答え】 (x+7)(x-7)
【高校レベル】数学I・IIで登場する因数分解の応用公式
中学の公式をマスターしたら、次は高校の「数学I」や「数学II」で登場する、少し複雑な公式です。特に3乗公式は符号(プラス・マイナス)で混乱しやすいので、ゆっくり確認しましょう。
| ⑤ x^2の係数が1 | x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b) |
| ⑥ 3乗の和 | a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) |
| ⑦ 3乗の差 | a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) |
| ⑧ 立方(3乗) | a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3 |
| ⑨ 立方(3乗)マイナス版 | a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3 |
⑤ x2の係数が1の場合
中学で習った公式④の応用版で、非常に重要です。「かけて ab(一番うしろの数)」「たして a+b(x の前の数)」になる2つの数 a と b を見つけるゲーム、と考えると分かりやすいです。
【例題】
x^2 + 7x + 10 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 「かけて +10」
- 「たして +7」
になる2つの数のペアを探します。 - かけて +10 になるペアは、(1, 10), (2, 5), (-1, -10), (-2, -5) です。
- この中で、たして +7 になるのは「+2」と「+5」のペアだけです。
- よって、a=2, b=5 として公式に当てはめます。
【答え】 (x+2)(x+5)
⑥ 3乗の和の公式
「(何かの3乗)+(別の何かの3乗)」という形を見つけたら、この公式です。
符号の覚え方:「(a+b)」は元の符号と同じ。後ろのカッコ (a^2 - ab + b^2) の真ん中は、元の符号と逆(マイナス)になると覚えると確実です。
【例題】
x^3 + 8 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 形を確認:x^3 は「x」の3乗。8 は「2」の3乗です。
- 公式を特定:a^3 + b^3 の形(a=x, b=2)だと分かります。
- 公式に適用:(a+b)(a^2 - ab + b^2) に当てはめます。
(x+2)(x^2 - x \times 2 + 2^2)
【答え】 (x+2)(x^2 - 2x + 4)
(※後ろの x^2 - 2x + 4 は、これ以上因数分解できません)
⑦ 3乗の差の公式
⑥のマイナス版です。「(何かの3乗)-(別の何かの3乗)」の形です。
符号の覚え方:「(a-b)」は元の符号と同じ。後ろのカッコ (a^2 + ab + b^2) の真ん中は、元の符号と逆(プラス)になります。
【例題】
x^3 - 27 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 形を確認:x^3 は「x」の3乗。27 は「3」の3乗です。
- 公式を特定:a^3 - b^3 の形(a=x, b=3)だと分かります。
- 公式に適用:(a-b)(a^2 + ab + b^2) に当てはめます。
(x-3)(x^2 + x \times 3 + 3^2)
【答え】 (x-3)(x^2 + 3x + 9)
⑧ 立方(3乗)の公式
これは展開公式 (a+b)^3 の逆です。項が4つあり、係数が「1, 3, 3, 1」のようになっていたら、この公式を疑います。
【例題】
x^3 + 6x^2 + 12x + 8 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 項が4つあり、すべてプラスであることに注目します。
- 両端を見る:x^3 は「x」の3乗。8 は「2」の3乗です。
- 「もしかして (x+2)^3 かも?」と仮説を立てます。
- 展開して確認します:(x+2)^3 = x^3 + 3 \times x^2 \times 2 + 3 \times x \times 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8
- 元の式と完全に一致しました。
【答え】 (x+2)^3
⑨ 立方(3乗)の公式(マイナス版)
⑧のマイナス版です。項が4つあり、符号が「+, -, +, -」と交互になっているのが特徴です。
【例題】
x^3 - 9x^2 + 27x - 27 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 項が4つあり、符号が + - + - と交互になっています。
- 両端を見る:x^3 は「x」の3乗。-27 は「-3」の3乗です。
- 「もしかして (x-3)^3 かも?」と仮説を立てます。
- 展開して確認します:(x-3)^3 = x^3 - 3 \times x^2 \times 3 + 3 \times x \times 3^2 - 3^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27
- 元の式と完全に一致しました。
【答え】 (x-3)^3
公式だけでは解けない!複雑な因数分解の実践テクニック5選(思考ステップ)
「公式は覚えたのに、テストで出てくる複雑な式になると、どれを使えばいいか分からない…」
これは、多くの学生さんが抱える最大の悩みです。
ここでは、どんな複雑な問題に出会っても迷わないための「考える順番(思考ステップ)」を5つのテクニックとして紹介します。因数分解は、このステップを上から順に試していくゲームだと思ってください。
因数分解を解くための「思考ステップ」
- ステップ1:まずは「共通因数」でくくれないか探す
- ステップ2:公式がそのまま使えないか確認する
- ステップ3:式の一部を「置き換え」(Aなど)でシンプルにする
- ステップ4:伝家の宝刀「たすきがけ」を試す
- ステップ5:最終手段:最も「次数」の低い文字で整理する
ステップ1:まずは「共通因数」でくくれないか探す
何よりも先に、これを試します。式がどんなに複雑に見えても、まず「全部の項に共通している文字や数字はないか?」を探すクセをつけてください。
共通因数でくくり出すだけで、式の形がシンプルになり、次に使うべき公式がパッと見えることがよくあります。
【例題】
3ax^2 - 12ay^2 を因数分解しなさい。
【解き方】
- パッと見て「2乗-2乗」の公式(④ a^2-b^2)が使えそうですが、グッとこらえます。
- ステップ1:共通因数を探します。
- 数字:3 と -12 → 「3」が共通
- 文字:a と x^2、a と y^2 → 「a」が共通
- よって、共通因数は「3a」です。
- 3a でくくり出すと、3a(x^2 - 4y^2) となります。
- ここでカッコの中 (x^2 - 4y^2) を見ると、公式④ a^2-b^2(x の2乗と 2y の2乗)が使える形になっていることに気づきます。
- 3a(x+2y)(x-2y)
【答え】 3a(x+2y)(x-2y)
(※先に公式④を使おうとすると、計算が複雑になってしまいます)
ステップ2:公式がそのまま使えないか確認する
共通因数がない、あるいは、くくり出した後の式を見て、先ほど紹介した9つの公式(中学の4つ+高校の5つ)がそのまま使えないかを確認します。
ステップ3:式の一部を「置き換え」(Aなど)でシンプルにする
「カッコのカタマリが何度も出てくる」「式が長すぎて見通しが悪い」
そんな時は、共通する部分を別の1文字(A や M など)で置き換えてしまうテクニックが非常に有効です。複雑な式を、見慣れたシンプルな形に一時的に変身させます。
【例題】
(x+y)^2 + 5(x+y) + 6 を因数分解しなさい。
【解き方】
- (x+y) というカタマリが共通していることに注目します。
- A = (x+y) と置き換えてみましょう。
- すると、元の式は A^2 + 5A + 6 と書き換えられます。
- これは公式⑤ x^2+(a+b)x+ab の形(かけて6、たして5)ですね。
- A^2 + 5A + 6 = (A+2)(A+3) と因数分解できます。
- ここで満足せず、必ず置き換えた A を元の (x+y) に戻します。
( (x+y) + 2 )( (x+y) + 3 )
【答え】 (x+y+2)(x+y+3)
ステップ4:伝家の宝刀「たすきがけ」を試す
x^2 の前に係数(1以外)がついている ax^2 + bx + c の形の式(例:2x^2 + 7x + 3)で、公式が使えない場合の切り札が「たすきがけ」です。
やり方さえ覚えれば、パズルのようで楽しくなりますし、これができると一気に上級者になれます。
【例題】
2x^2 + 7x + 3 を因数分解しなさい。
【解き方】
- x^2 の係数(2)と、定数項(3)に着目します。
- かけて 2 になるペア(左側)と、かけて 3 になるペア(右側)を縦に書きます。
(例)1 1
2 3 - これらを「たすき(バツ印)」のように斜めにかけて、足し算します。
- 1 \times 3 = 3
- 2 \times 1 = 2
- 3 + 2 = 5
- この結果「5」が、真ん中のx の係数(7)と一致すれば成功です。今回は一致しませんでした(失敗)。
- では、右側のペアを (3, 1) の順に変えてみます。
1 3
2 1 - 再度たすきがけします。
- 1 \times 1 = 1
- 2 \times 3 = 6
- 1 + 6 = 7
- 真ん中の係数「7」と一致しました!(成功)
- 答えは、横のペアをそのままカッコに入れます。
(1x + 3)(2x + 1)
【答え】 (x+3)(2x+1)
ステップ5:最終手段:最も「次数」の低い文字で整理する
ステップ1〜4のどれも使えない…式に x も y も z も入っていて、ぐちゃぐちゃだ…
これが最終手段です。
次数に注目し、式の中に登場する文字の中で「最も次数が低い文字」を1つ見つけます。そして、その文字について「降べきの順」に整理(並べ替え)します。
【例題】
x^2 + xy + 2x + 3y - 3 を因数分解しなさい。
【解き方】
- 次数チェック:x は x^2 があるので「2次」。y は y^1 しかないので「1次」です。
- 最低次数の文字:y の方が次数が低いので、y が「主役」です。
- y が「ついている項」と「ついていない項」に分けて、 y でくくります。
(xy + 3y) + (x^2 + 2x - 3)
= (x+3)y + (x^2 + 2x - 3) - 後ろの「ついていない項」 (x^2 + 2x - 3) だけで因数分解できないか考えます。
(かけて-3、たして+2 なので、(x+3)(x-1) になります) - 式に戻します。
(x+3)y + (x+3)(x-1) - 全体をよく見ると、 (x+3) という「新しい共通因数」(ステップ1)が生まれていることに気づきます!
- この (x+3) で全体をくくり出します。
(x+3) \{ y + (x-1) \}
= (x+3)(y + x - 1)
【答え】 (x+3)(x+y-1) (アルファベット順に並べ替えることが多いです)
因数分解に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、因数分解を学ぶ学生さんから特によく聞かれる質問や、細かい疑問についてお答えします。
「たすきがけ」がうまくいく組み合わせを見つけるコツは?
たすきがけ(ステップ4)は、慣れるまで正しいペアを見つけるのが大変ですよね。コツは「探す範囲をしぼること」です。
- 符号に注目する:
- 一番うしろの項(定数項)がプラス(例: ... + 3)なら、ペアは(+, +)か(-, -)です。真ん中の項がプラスなら(+, +)、マイナスなら(-, -)に決まります。
- 一番うしろがマイナス(例: ... - 3)なら、ペアは必ず(+, -)の組み合わせになります。
- 数字の候補を減らす:
- x^2 の係数が 6 の場合、(1, 6) と (2, 3) のペアが考えられますが、まずは差が小さい (2, 3) のペアから試す方が、早く正解にたどり着くことが多いです。
3乗の公式がどうしても覚えられません…
a^3 \pm b^3(項が2つ)と (a \pm b)^3(項が4つ)は、確かに混乱しやすいです。
符号のルールを決めて覚えるのがおすすめです。
- a^3 + b^3 (項が2つ)
- (a+b)(a^2 - ab + b^2)
- 最初のカッコ (a+b) は、元の符号と同じ。
- 後ろのカッコ (... - ab ...) の真ん中は、元の符号と逆。
- a^3 - b^3 (項が2つ)
- (a-b)(a^2 + ab + b^2)
- 最初のカッコ (a-b) は、元の符号と同じ。
- 後ろのカッコ (... + ab ...) の真ん中は、元の符号と逆。
この「最初は同じ、次は逆」というルールで覚えてみてください。
因数分解と「展開」の違いってなんですか?
この2つは、まったく逆の操作です。
- 展開:
- (x+2)(x+3) \rightarrow x^2 + 5x + 6
- (かけ算の形)を(足し算・引き算の形)にバラすこと。
- 因数分解:
- x^2 + 5x + 6 \rightarrow (x+2)(x+3)
- (足し算・引き算の形)を(かけ算の形)にまとめること。
例えるなら、「プラモデルを組み立てる(展開)」のと「完成したプラモデルをパーツごとに分解する(因数分解)」のような関係です。
まとめ
お疲れ様でした。この記事では、因数分解でつまずきやすい学生さんのために、中学・高校で習う公式の一覧と、複雑な式も解けるようになるための「5つの実践テクニック(思考ステップ)」を解説しました。
因数分解は、単なる暗記ゲームではありません。
- まず「共通因数」でくくる
- 公式が使えないか見る
- 「置き換え」でシンプルにする
- 「たすきがけ」を試す
- 「最低次数の文字」で整理する
という、解法を試す「順番」が何よりも大切です。この思考ステップを身につければ、どんな応用問題に出会っても、解き方の方針が立てられるようになります。
因数分解は、これから学ぶ2次方程式や関数分野の土台となる重要な道具です。この記事をガイドに、ぜひ「解ける!」という自信をつけてください。


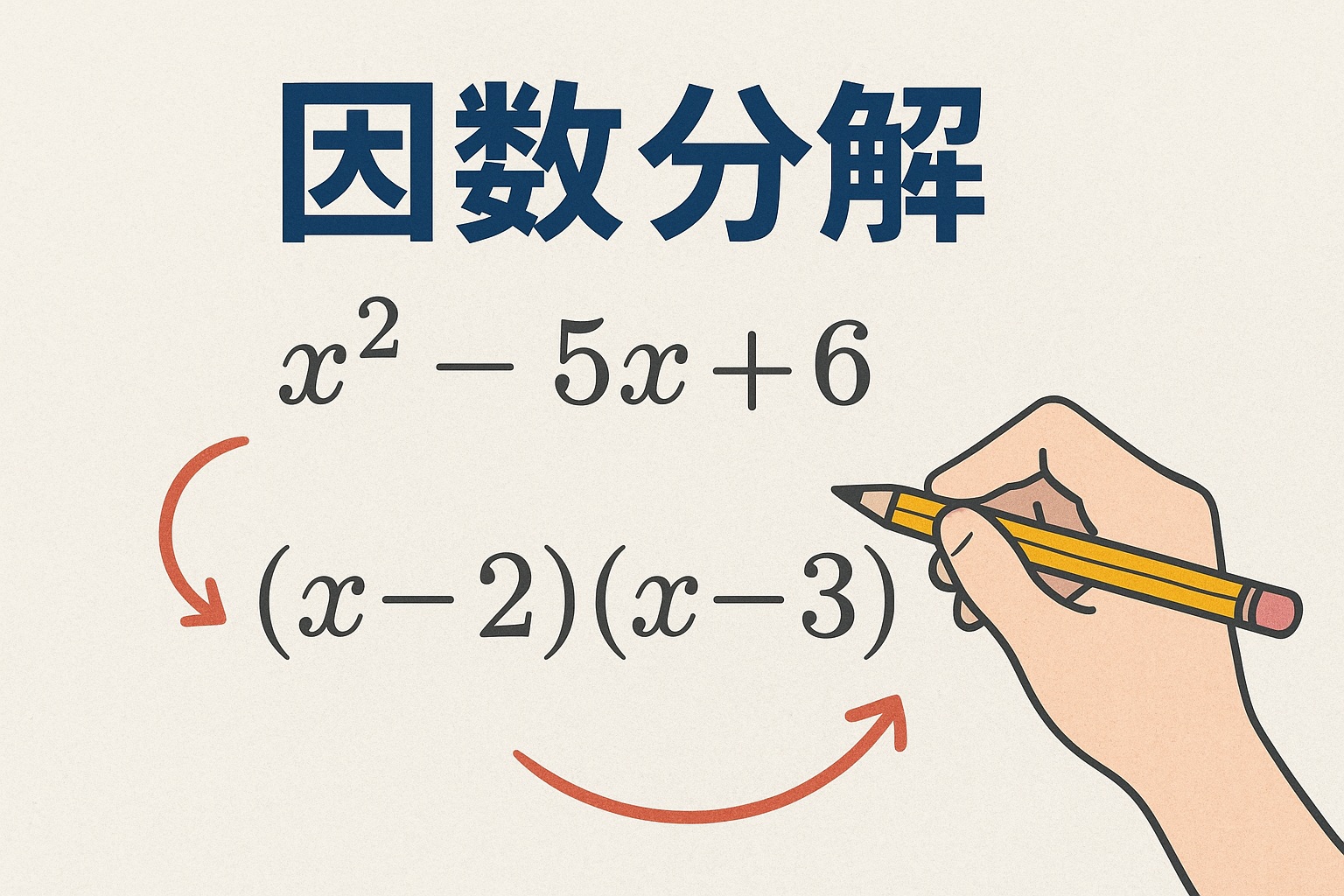


コメント